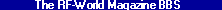 | ||
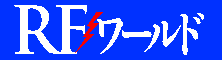 |
RFワールド読者の掲示板Ⅱ
無線と高周波に関することを中心に、それ以外の話題も含めて、何でも書き込みOKの掲示板です。初めての方もネチケットを守って、お気軽にご参加下さい(^^)/
|
森榮 - 19/2/23(土) 11:01 - |
▼Hiroyuki Naitoさん:
>お世話になります。
>
>53頁の図6_2(添付参照)のサブキャリアのI波形を生成するのに、サブキャリアのCOSとSIN波形がなぜ必要なのかすぐにはピンときませんでしたが、67頁のベースバンドI波形の式(6.1)を見つけて以下のように解釈しました。
>
> I(t)=cos{2π(f2)t+(π/2)N} …(6.1)
>
> f2はサブキャリア(0~15)のいずれかの周波数。
> NはQPSK変調の2ビット入力データ(0~3の整数)。
>
>N=0の場合 I(t)=cos(2π(f2)t+0) → COS
>N=1の場合 I(t)=cos(2π(f2)t+90°) →-SIN
>N=2の場合 I(t)=cos(2π(f2)t+180°)→-COS
>N=3の場合 I(t)=cos(2π(f2)T+270°)→ SIN
>
>となり表6.4と一致しました。サブキャリアのI波形生成は、入力データによって符号付きのCOS、SIN波形を択一していく操作になると思われますが、間違っていないでしょうか。
お世話になります。
Naito様がおっしゃいますとおり、本記事のQPSKサブキャリアの生成は、
SIN,COSいずれかを選び出して、正符号もしくは負符号をつけることで、
実現しております。FPGAのVerilogソースコードにつきましても、このコンセプトをもとに実装されております。
余談でございますが、16QAM、256QAMなど、変調が複雑になってきますと、
もう少し演算操作が複雑になってきます。
サブキャリア生成の際に、SIN,COSに振幅の重みを持たせて、足し合わせる必要があります。
>お世話になります。
>
>53頁の図6_2(添付参照)のサブキャリアのI波形を生成するのに、サブキャリアのCOSとSIN波形がなぜ必要なのかすぐにはピンときませんでしたが、67頁のベースバンドI波形の式(6.1)を見つけて以下のように解釈しました。
>
> I(t)=cos{2π(f2)t+(π/2)N} …(6.1)
>
> f2はサブキャリア(0~15)のいずれかの周波数。
> NはQPSK変調の2ビット入力データ(0~3の整数)。
>
>N=0の場合 I(t)=cos(2π(f2)t+0) → COS
>N=1の場合 I(t)=cos(2π(f2)t+90°) →-SIN
>N=2の場合 I(t)=cos(2π(f2)t+180°)→-COS
>N=3の場合 I(t)=cos(2π(f2)T+270°)→ SIN
>
>となり表6.4と一致しました。サブキャリアのI波形生成は、入力データによって符号付きのCOS、SIN波形を択一していく操作になると思われますが、間違っていないでしょうか。
お世話になります。
Naito様がおっしゃいますとおり、本記事のQPSKサブキャリアの生成は、
SIN,COSいずれかを選び出して、正符号もしくは負符号をつけることで、
実現しております。FPGAのVerilogソースコードにつきましても、このコンセプトをもとに実装されております。
余談でございますが、16QAM、256QAMなど、変調が複雑になってきますと、
もう少し演算操作が複雑になってきます。
サブキャリア生成の際に、SIN,COSに振幅の重みを持たせて、足し合わせる必要があります。
584 hits
| ▼ | [RFW41]図6_2のベースバンド波形の生成 Hiroyuki Naito 19/2/19(火) 20:00 |
|
| Re:[RFW41]図6_2のベースバンド波形の生成 森榮 19/2/23(土) 11:01 | ≪ |
60,645